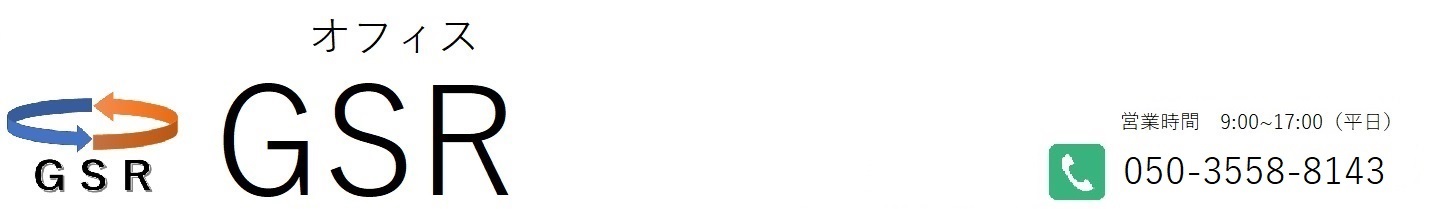こんにちは行政書士の松本@officegsrです。
今回は「相続の手続きの流れ」について簡単にその概要を説明します。
高齢の親が病気やケガをした場合、亡くなったときの相続の手続きはどうなるのかなと心配になりますよね。
相続のおおまか流れを理解しているだけでも、心の準備ができます。
今回の動画でわかる事は、
- 相続の発生する時期
- 相続が発生して最初にすべきこと
- 相続が発生しておこなう必要な手続きの流れ
について簡単にお話しします
相続手続きの流れについて知りたい方は必見です。
(この記事は2023年1月現在の法令にもとづき記載しています)
動画での解説はこちらです。
相続の開始時期について

今回は、沖縄花子さんのご家族を例にお話し、妻に財産があるパターンでお話します。
大変残念ながら花子さんがとある事情で亡くなってしまったとします。

相続というのは、花子さんが亡くなった瞬間に発生します。
花子さんが持っている、預貯金・土地建物等の不動産、あるいは誰かに貸したお金という権利や、銀行へのローンなど返済の義務等の相続財産について、花子さんが亡くなった瞬間に「相続」が発生するんです。
ただ花子さんが亡くなった瞬間には、
「どの財産を誰が引き継ぐのか」
そして
「花子さんの相続人は一体誰なのか
というのは、花子さんが亡くなった時点でははっきり決まっていません。
そのため、相続の手続きについては、その流れを理解して1つずつしっかりと進めることが重要です。
相続には「手続きの期限」があります。
この相続手続きについては、
- 3ヶ月
- 4ヶ月
- 10ヵ月
という3つの大きな期限があります。

3か月の期限
まず一つ目「3か月の期限」
花子さんが亡くなって3ヶ月以内にすること。
それは、おおかたの財産全体を把握して、
受け取る財産の方が大きいのか、あるいは借金の方が大きいのか
ということを確認することです。
花子さんの相続人たちは、この
相続財産を引き継ぐのかどうか
ということを考えなければなりません
ちょっと横道にそれますが、
「遺言書(ユイゴンショ)」
のことを法律の専門家は
「遺言書(いごんしょ)」
とよく言います。
専門家に相談した時「イゴンショ」という言葉が出てきたら「ユイゴンショ」のことだと理解してください。
以上のように、花子さんが亡くなり相続が開始されたとき、相続人はまず
「3ヶ月以内に相続するのかしないのかを判断する必要」
があります。
そして「相続する」と決めた場合、この相続財産を相続人で分割する必要があります。
この相続財産を分割するのに「花子さんの遺言書があるかないか」で、手続きの流れが変わってきます。
まず花子さんの遺言書があると言う場合。
この相続財産の分割とは、亡くなった花子さんの気持ちを尊重する必要ありますので、遺言書をもとに相続財産を分割することになります。
もし花子さんの遺言書がないと言う場合。
花子さんの相続人全員で遺産分割協議書とを作成して、遺産分割協議をする必要があります。
例えば、花子さんの相続人が花子さんの夫と成人した長男、長女の2人合計3人だった場合。

この夫と、長男、長女の3人で、誰がどのような財産をどれぐらい受け継ぐのかということを話し合って、これをしっかりと遺産分割協議書の様式で文書を作成する必要があります。
遺言書をもとに遺産分割したり、相続人全員で話し合って遺産分割協議をした結果を踏まえて、必要があれば相続税を納付します。
相続税を納付するかしないかというのは相続財産の金額によってわかれてきます。
例えば、相続税の控除(割引みたいなもの)を利用して相続税が0円となった場合でも、申告する必要がありますので、注意が必要です。
続いて、花子さんが亡くなって3ヶ月以内に相続した場合。
この場合は、相続しない「相続放棄」と言う手続きが必要となります。
花子さんが亡くなったあと3ヶ月以内に、家庭裁判所へ
「私は相続放棄します」
と言う申し立てを行う必要があります
また花子さんの財産を調べた結果、プラスの財産があるのかマイナスの財産があるのかよくわからないけど、プラスの財産があるのであれば相続したいという場合は、
「限定承認をします」
という、申し立てを家庭裁判所におこなう必要があります。
「相続放棄」は相続人が何人いても「私は相続しません」とその人が申立したら、その人は相続放棄を選ぶことができますが「借金と財産を比べて財産が多い場合に相続します」という「限定承認」の場合には、「相続人全員が合意」をした上で、共同で家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。
つまり、限定承認の場合相続人の中で反対する人が1人でもいる場合には、限定承認はできないものとなっています。
これが最初の3か月の期限です。
4か月の期限
次に相続手続きの4か月の期限について説明します。
例えば花子さんがアパート経営をしている大家さんだった場合。
アパート経営している方は毎年1年分の収益について、確定申告を行っています。
この確定申告を行っている方が亡くなった場合、亡くなったあと4か月以内に「準確定申告」を行う必要があります。
通常の確定申告は毎年2月から3月にかけて行われます。
もし、7月に花子さんが亡くなった場合
「確定申告は毎年2月から3月だから来年だな」
と考えると間違いとなってしまいます。
準確定申告は、
「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければならない」
となっています。
「相続の開始を知った日」から4か月以内です。
知らなかったらカウントが始まりませんが、一般的には人が亡くなったときはその日がわかりますよね。
これが「4か月の期限」です。
10カ月の期限
先ほどお話しした3か月以内の期限を通り越して、
「相続する」
となった場合。
あるいは
「限定承認をする」
となった場合。
「相続財産から借金などのマイナスの財産を引いてプラスの財産が残った」場合には、遺言書のとおりあるいは相続人の全員で遺産の分割協議を行った上で遺産分割協議書を作成し、相続税を納付する必要があれば相続税の納付、相続税の納付をする必要がない場合は相続税の納付が行われません。
この相続税の納付期限が
「亡くなってから10か月以内に納付する」
と決まっています。
申告が10か月以内ではありません。
相続税の納付が10か月以内です。
これが、
「10か月もあるのかー」
と思われがちですが、初七日、四十九日の法要などで最初の1,2か月はバタバタしますし、その後相続するしないの判断の3か月の期限、準確定申告の4か月の期限がやってきて
「さぁ遺産をわけよう」
となると残り数か月ということがよくあります。
相続税の計算をするとき、土地の場合国税庁が発表してる相続税路線価というものでその土地の財産価格をおおよそはじき出すことができますが、その土地の形によって評価額がかわったりしますので、その調査にもある程度時間はかかります。
被相続人が亡くなったあと10カ月以内に相続税の申告・納付まで終える必要がある。
これが10カ月の期限です。
相続財産の名義変更

最後に重要な事は、
相続財産というのは亡くなったなくなった花子さんの名義のままになっているので、これを相続財産を引き継ぐ人の名義に変更する
ことです。
自宅などの土地建物でいえば、不動産の名義を花子さんの夫が引き継ぐのであれば、夫の名義に変えないといけないですし、花子さんの預貯金を長男、長女で半分ずつ分けると言うことであれば、長男と長女が銀行で花子さんの口座から自分の口座への移管手続きをしなければなりません。
これらの各手続きで「私の名義になりました」と証明する最も重要な書類が、
- 遺言書または遺産分割協議書
です。
もし遺産分割協議で花子さんの長男が自宅の土地建物相続すると決めた場合、花子さんの長女が勝手に法務局に
「土地建物は私が相続したので登記の名義を私に変えてください」
と勝手に登記の手続きを行ったとしても、遺産分割協議書でその長女が確かに相続すると協議された内容が確認できないと、法務局では登記の変更手続きを行ってくれません。
「遺産分割協議書」は、厳格な様式が求められます。
例えば、印鑑が実印であることが法務局や銀行での手続きに求められています。
まとめ

相続は亡くなった人が亡くなったその瞬間から発生することがおわかりいただけましたか。
そして
・亡くなって3か月以内にある程度相続財産を調べて相続するしないを判断する必要がある
・被相続人が確定申告をおこなっていれば、亡くなったあと4か月以内に準確定申告をおこなう必要がある
・遺言書や遺産分割協議書を持って相続財産を分割した結果、相続税を納付する必要がある場合には、10カ月以内に相続税の申告納付をする必要がある
ことがわかりました。
そして「相続する」場合は、遺言書があるのかないのかということも重要でした。
遺言書がある場合には、亡くなった花子さんの気持ちを尊重することが大切なことなので、その遺言書にそって遺産分割が行われることが一般的です。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行った上で遺産分割協議書を作成する必要があります。
特別な控除などを利用して相続税が発生しないと言う場合でも、税務署に相続税申告する必要がありますので、まずは専門家に相談しましょう。
そして被相続人が亡くなって相続税納付までの手続きが完了した後でも、相続財産が被相続人の名義ままですので、不動産の名義を変更したり銀行口座の預貯金等を相続人に移管する必要がありました。
以上のように、相続が発生した場合は、いくつかの期限がやってきてさまざまなことを考えて実行しないといけないので、早め早めに専門家に相談するとスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
本日も最後までごご覧いただきありがとうございました。