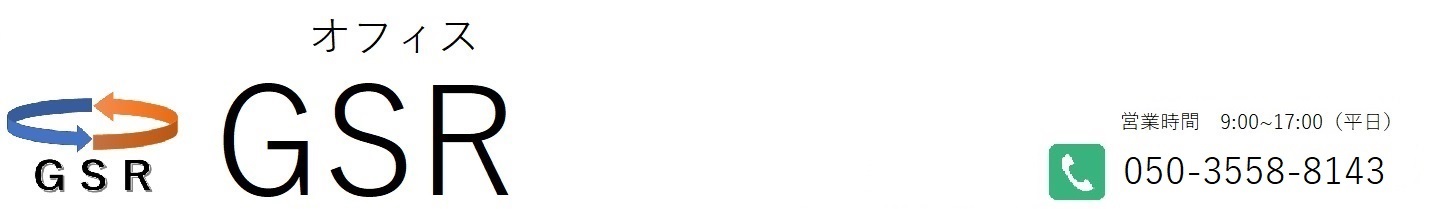こんにちは。
社会保険労務士の松本@officegsrです。
今日は年次有給休暇の取得や基本的なルールについて説明します。
「この会社に入って半年がたつけど、私っていつから年休使えるのかな」
とか、
「結婚したときには特別な年休が使えるのかな」
と年次有給休暇についてよくわからないことってありますよね。
今日はその疑問についてズバッとお答えします。
今回の記事をご覧いただくことで、
- 年次有給休暇が発生する要件と与えられる日数
- パートアルバイトの年休について
- そして結婚休暇などの特別休暇とはどういったものか
について理解することができます
年次有給休暇の基本的なルールについて、知りたい方は必見です。
年次有給休暇の発生要件と付与日数について

年次有給休暇の発生要件と付与日数
年次有給休暇は労働基準法という法律でそのルールが定められています。
労働基準法では、
①労働者は雇い入れの日から6ヶ月継続して雇われている
②全労働日の8割以上出勤している
この2つの要件を満たしていれば、年次有給休暇を取得することができます。
雇い入れの日というのは入社日のことです。
全労働日とは、雇用契約で労働の義務が発生している日のことを言います。
会社の休日が土日祝祭日休みであれば、休日以外の出勤をする必要がある日のすべての日数で8割以上出勤していることが必要です。
次に年次有給休暇の、付与日数についてみていきます。
使用者は労働者が雇い入れの日から6カ月間継続勤務し、その6カ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
この対象労働者には、管理監督者や契約社員も含まれます。
入社して、
- 継続勤務年数6ヶ月:付与日数10日
- 勤続年数1年6ヶ月:付与日数11日
- 勤続年数2年6ヶ月:付与日数12日
- 勤続年数が3年6ヶ月:付与日数14日
- 勤続年数が4年6ヶ月:付与日数16日
- 勤続年数が5年6ヶ月:付与日数18日
- 勤続年数が6年6か月:付与日数20日
の年数がたつと、年次有給休暇の付与となります。

パートタイマーやアルバイト従業員など決められた労働日数が少ない労働者に対する付与日数
パートタイマー・アルバイトなど、1週間の労働日数が正社員やフルタイムの労働者と比べて少ない方については、年次有給休暇の日数は、1週間の勤務日数または1年間の勤務日数に応じて日数が付与されます。
これを
比例付与(ひれいふよ)
と言います。
これは使用者と労働者がお互いで約束した働くべき日数に応じて、年次有給休暇の日数も変わるということです。
比例付与の対象となるのは、決められた労働時間が週30時間未満で1週間の労働日数は4日以下または年間の決められた労働日数が216日以下の労働者です。
週の日数や勤続年数に応じて細かくわかれます。

週3日のパートタイマーの方が入社後の6か月間で全労働日の8割以上を出勤した場合には、5日間の年次有給休暇を取得できます。
では、1日5時間で週5日働いている人はどうなるでしょうか。
これは週5日出勤というのは正社員やフルタイムと出勤の日数と同じになるので、6か月経過後から10日の年次有給休暇が付与されます。
でも1日5時間の10日間です。
年次有給休暇を使うときのルール

年次有給休暇付与について守るべきことは3つあります。
1つ目が年次有給休暇を与えるタイミングです
年次有給休暇は、労働者が請求する「時季」に与えることとされています。
この時季というのは、期間の時期ではなく「時季」という漢字を使います。
労働者が具体的な日にちを指定した場合には、使用者が持っている「時季変更権」というものによる場合を除いて、労働者が指定した日に年次有給休暇を与える必要があります。
時季変更権とは、
「使用者は労働者から年次有給休暇を請求された時季に、年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、例えば同じ時間に多数の労働者が休暇を希望したため、その全員に休暇を付与することが難しい場合などには、ほかの時季に年次有給休暇の時季を変更することができる」
使用者の権利です。
変更することはできても「与えない」ということは認められていません。
「事業の正常な運営を妨げる場合」というのも、会社の業種、規模によってさまざまですので、一概にはいえませんが、ただこの時季変更権は簡単に使えるものではなく、シフトを変わってくれる人がいないという場合でも、使用者がまず代わりの労働者の配置を検討する必要があります。
2つ目に年次有給休暇は、その年にあまった年休は次の年度に繰越ができます。
年次有給休暇の請求権の時効は2年間です。
前年度に消化できなかった年次有給休暇は翌年度に与える必要があります。
例えば今年10日年次有給休暇が与えられた労働者が5日の年次有給休暇を残した場合には、翌年の年次有給休暇が、入社後1年6か月目には11日プラス5日となって16日の年次有給休暇日数でスタートとなります。
そして3点目が不利益取扱いの禁止です。
使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して、給与を引き下げたり、その他の不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません。
具体的な例を挙げますと、皆勤手当や賞与の額の算定に際して、年次有給休暇取得した日を欠勤、または欠勤に準じた取り扱いにするなど不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません。
その他の年休の制度

年次有給休暇の計画的付与
これは会社が計画的に取得日を決めて年次有給休暇を与えることが可能になる制度です。
ただし、労働者が自ら請求取得できる年次有給休暇を最低でも5日間を残す必要があります。
この制度の導入については、会社と労働者代表との労使協定という協定の締結が必要です。
半日単位の年次有給休暇
実は、年次有給休暇は1日単位で取得することが原則です。
しかし、労働者が半日単位での取得を希望し、使用者が同意した場合であれば、1日単位取得の疎外とならない範囲で、半日単位で年次有給休暇を取ることが可能です。
これとは別に、時間単位の年次有給休暇をとることができる会社も多いと思います。
年次有給休暇は1日単位で取得することが原則と先ほどお話しましたが、労働者が時間単位での取得を請求した場合には、年に5日を限度として時間単位で年次有給休暇を取ることが可能です。
これも原則外の制度なの、時間単位で与えることを可能にするためには、会社と労働者代表による労使協定という協定の締結が必要です。
「特別休暇」とは?
その他会社によっては特別休暇という名前の休暇制度を導入しているところもあると思います。
これは法律で決められた年次有給休暇に加えて、休暇の目的や取得形態を会社が任意で自由に設定できる会社独自の休暇制度です。
例えば、結婚したときの結婚休暇、身内が亡くなったときの忌引き休暇などが該当します。
子どもが新型コロナに感染した、という場合にも学校等休業対応の特別休暇というのもありますね。
この特別休暇の制度は会社が任意に決められる休暇制度なので、有給か無給というのも会社が設定できます。
特別休暇が無給の場合でも法律に違反するものではありません。
そして、時間単位年次有給休暇と特別休暇については、2019年4月から義務付けられている年5日の年次有給休暇取得義務制度の対象とはならないので、注意が必要です。
これは、10日以上年次有給休暇が与えられた労働者については、会社は時季を指定してでも年5日以上年次有給休暇を取得させなければならない、という制度です。
時間単位の年次有給休暇を足し算して、通算5日になったとしても、この年5日年次有給休暇取得義務を満たしたことにはなりません。
半日または1日など、しっかり休んだ日が年5日の対象となります。
まとめ

今回の記事では、
- 年次有給休暇の発生要件と付与日数
- 年次有給休暇を与えるときに関する基本的なルール
- その他の年次有給休暇制度
について説明しました。
パートタイマー、アルバイト従業員にも労働日数に応じて年次有給休暇があること、労働者が指定した時季に与える必要があることなどがわかりました。
そして、年次有給休暇の制度において、1日単位が原則だが半日単位も認められること、時間単位の年休を利用する場合は労使協定の締結が必要であることがわかりました。
年次有給休暇の計画的な付与についても労使協定の締結が必要でしたね。
法定の年次有給休暇とは別に「特別休暇」というものがあることもわかりました。
特別休暇は会社が任意で定める制度なので、有給、無給は会社が決めています。
記事をご覧になったみなさまご自身の会社では年次有給休暇のルールについて、適正に運用されていますか?
労働者がリフレッシュすることで、労働生産性は向上します。
しっかり休むことができる体制をつくることが会社の責務です。
本日も最後までごご覧いただきありがとうございました。