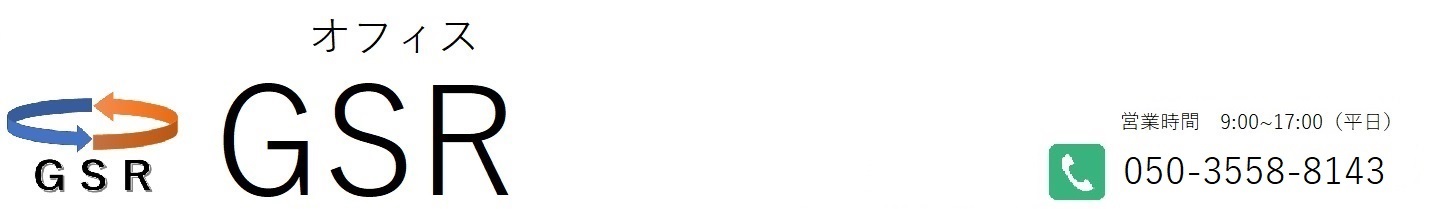こんにちは、沖縄の社労士、行政書士、1級FP技能士の松本@officegsrです。
令和6年度補正予算により措置された
「介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」
は、多くの介護事業所様にとって人材確保や職員の定着に向けた大きな支えとなり得る制度です。
この補助金の主要な使い道の一つとして、「介護職員等への人件費改善」が挙げられます。
しかし、「具体的に誰を対象に人件費改善を行えるのだろうか?」「いつまでに実施すれば良いのだろうか?」といった疑問をお持ちの経営者、管理者もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、この補助金に関する「国のQ&A」で示された情報の中から、特に人件費改善の実施時期と対象範囲に関する重要なポイントを抜粋し、分かりやすく解説します。
介護人材確保・職場環境改善等事業補助金の交付申請を行った事業所は必見です。
介護人材確保・職場環境改善等事業補助金における人件費改善の実施
介護人材確保・職場環境改善等事業補助金における人件費改善の実施におていは、次の点に注意が必要です。
ここでは、国のQ&Aで示された内容をもとに、ポイントをお伝えします。
交付額により人件費の改善や職場環境改善を行う場合、いつまでに行う必要があるのか
介護人材確保・職場環境改善等事業補助金を交付申請の補助額による人件費の改善や職場環境改善は、基準月から各自治体が定める実績報告書の提出までに行う必要があります。
たとえば、沖縄県では令和7年10月31日を実績報告書の提出期限と定めています。
(基準月とは、原則令和6年 12 月ですが、令和7年1月、2月又は3月も選択可能です)
ただし、介護事業所に対する緊急支援という趣旨から、特に人件費の改善については、可能な限り速やかに実施することが推奨されています。
補助金が交付されたら、夏季賞与の支給時期も踏まえながら、早めに職員への還元を検討しましょう。
法定福利費等の事業主負担の増加分は、人件費の改善に含めてよいか
これは事業所にとって非常に嬉しいポイントです。
補助金を使って人件費を改善(一時金等を支給)すると、それに伴って社会保険料などの法定福利費の事業主負担分も増加します。
この増加した法定福利費等の事業主負担分についても、補助金による人件費改善の一部として含めることが可能です。
これにより、事業所の持ち出し負担を軽減しながら、職員の人件費改善に繋げやすくなります。
ただし、法定福利費の計算には合理的な計算が必要となってきます。
不当に高額な法定福利費の算定は、制度の趣旨に沿わない賃金改善と指摘される可能性があるため、注意が必要です。
補助金を人件費の改善に充てる場合、介護職員以外の職員への配分は可能か
補助金による人件費改善は、基本的には介護職員への配分を想定しています。
これは、介護の現場を支える職員の処遇改善を優先するためです。
しかし、同一事業所において雇用されている職員であれば、介護職員以外の職員(事務職員、相談員、看護職員など)も含めて、すべて対象とすることが可能であるとされています。
ただし、配分にあたっては、事業所内の状況や貢献度などを考慮し、職員間で不公平感が生じないよう、慎重に検討することが重要です。
どのような基準で配分を行うか、事前に職員へ説明することも有効でしょう。
法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護に従事していない職員について、補助額に基づく人件費改善や職場環境改善の対象に含めることは可能か
いくつかの事業所を抱える法人組織の場合が該当します。
法人本部などで働く、直接介護に従事していない職員を対象にできるか、という問いです。
これについては、補助金の対象となっているサービス事業所等における業務に携わっていると判断できる法人本部の職員については、人件費改善や職場環境改善の対象に含めることが可能です。
例えば、対象事業所の経理や人事労務、運営管理などを担当している場合などが考えられます。
一方で、補助金の対象となっていないサービス事業所等(例えば、補助金の対象外となるサービス種別のみを提供している事業所など)の職員は、本補助金を原資とする人件費改善等の対象に含めることはできません。
法人本部の職員を含めるかどうかは、その職員が補助対象事業所の運営にどの程度関わっているかを考慮して判断する必要があります。
まとめ

介護人材確保・職場環境改善等事業補助金
今回お伝えした制度の概要で重要な活用ポイントは次の点です。
- 人件費改善は可能な限り速やかに、実績報告書提出期限までに実施。
- 人件費改善に伴う法定福利費の事業主負担増加分も補助対象に含めることが可能。
- 同一事業所の雇用職員であれば、介護職員以外も対象に含めることが可能(ただし、介護職員への配分が基本)。
- 法人本部の職員も、対象事業所の業務に関わっていれば対象になり得る。
補助金をどのように活用し、どの職員に配分するかを検討する上で、参考になりましたか?
法定福利費の増加分を含められる点や、介護職員以外の職員も対象になり得る点は、事業所の状況に応じた柔軟な活用を検討する参考材料となるでしょう。
ただし、これはあくまで国のQ&Aを参考にした情報です。
実際の補助金の詳細な要件や申請手続きにつていは、各都道府県が実施主体となっています。
の具体的な実施方法については、都道府県が「交付要綱」を定めていますので必ず各都道府県のHPをご確認ください。
この補助金を上手に活用し、介護人材の確保と、職員の皆様がより働きがいを感じられる職場環境の実現に繋げてください。
介護職員等処遇改善加算制度は複雑です。
人事労務管理制度の構築には、社会保険労務士などの専門家への相談をおすすめします。
本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。
沖縄県浦添市の社会保険労務士、行政書士、1級技能士である松本崇が、介護人材確保・職場環境改善等事業補助金について解説しました。
企業の労務管理に関するご相談は、ぜひ社労士オフィスGSRまでお気軽にお問い合わせください。